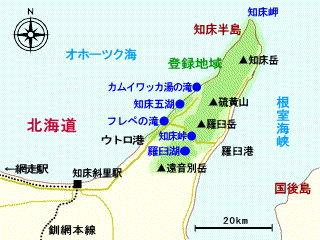厳冬の知床半島
流氷が接岸する北半球では世界最南端の知床、流氷とともにやってくるプランクトン、それを餌にする魚の大群、それを目当てにオジロワシ、オオワシ、アザラシが海を渡ってくる。秋になると海の豊かさを蓄えたサケが川を遡上し知床の森を豊かにする。流氷は海から山への命の輪を育んでいる。

大海原にただよう流氷
流氷は北西の季節風に押されてオホーツク海を南下してくる。いったん接岸しても、風の方向や潮の流れによって沖に離れることがある。写真は大海原にただよう流氷の様子、様々な姿となっている。

海岸に接岸した流氷
北西の季節風に押されてオホーツク海を南下してきた流氷、ウトロ海岸を埋めつくし次々と押し寄せる流氷の圧力で丘のように盛り上がっている。流氷と流氷がこすれるギュウギュウという低く重い音が聞こえた。

ウトロ港を埋めつくす流氷
知床半島が流氷を受け止めるようにオホーツク海に突出ているので、海岸に接岸した流氷はウトロ港を埋めつくす。港からは船を出すことができなくなる。

オオワシ
知床は、国際的に希少種とされているシマフクロウの生息地であり、天然記念物に指定されているオオワシやオジロワシの越冬地になっている。写真は全長がオス88cm、メス102cmもあるオオワシ、冬になると北方のカムチャッカ半島などから渡ってくる。

エゾシカの一群
特異な生態系、生物多様性が評価された知床、さまざまな野生動物に出会うことができる。写真はフレペの滝への遊歩道で出会ったエゾシカの一群、ニホンジカの中では最も大型で雄の角も大きく立派、冬毛は地味な灰褐色。この地は、オホーツク海から吹き付ける強風で森が育たず草原になっている。

知床連山
標高1600mほどの知床連山(しれとこれんざん)、標高はさほど高くないが本州の3000m級の山々と同じ環境をもつ。羅臼岳から半島の先に向け三ツ峰、サシルイ岳、オッカパケ岳、知円別岳、硫黄山、知床岳と連なる。中央の山は硫黄山、手前の草原は開拓跡地で森の再生を試みているが寒冷地のため樹木が育たない。

氷結したフレペの滝
オホーツク海に面した高さ100mの断崖を流れ落ちるフレペの滝、地下水が断崖の割れ目から涙のように静かに流れることから「乙女の涙」とも呼ばれている。最高温度でも氷点下以下という厳冬のなか、水量の少ないフレペの滝は季節風に巻き上げられながらゆっくりと凍りついていた。